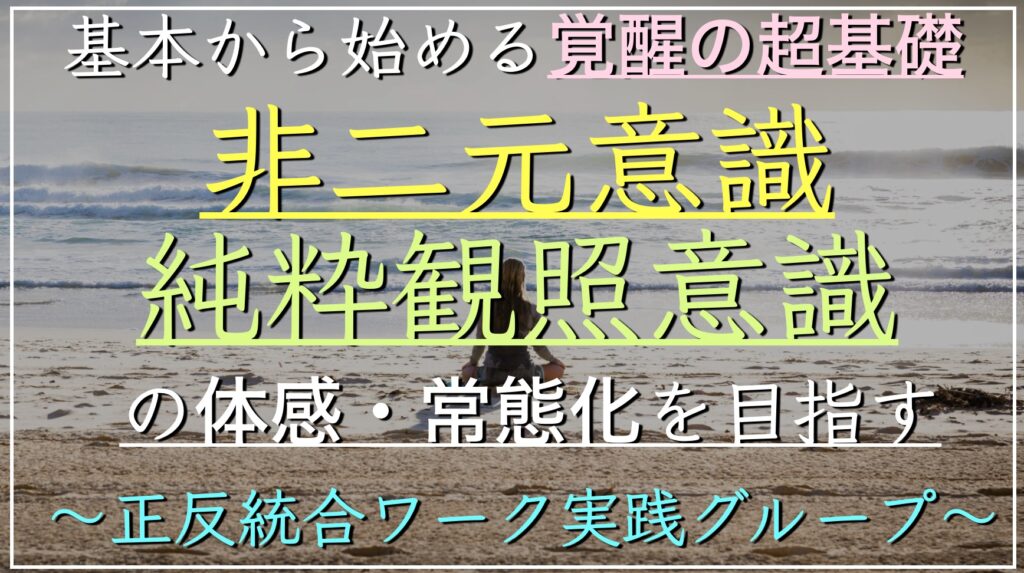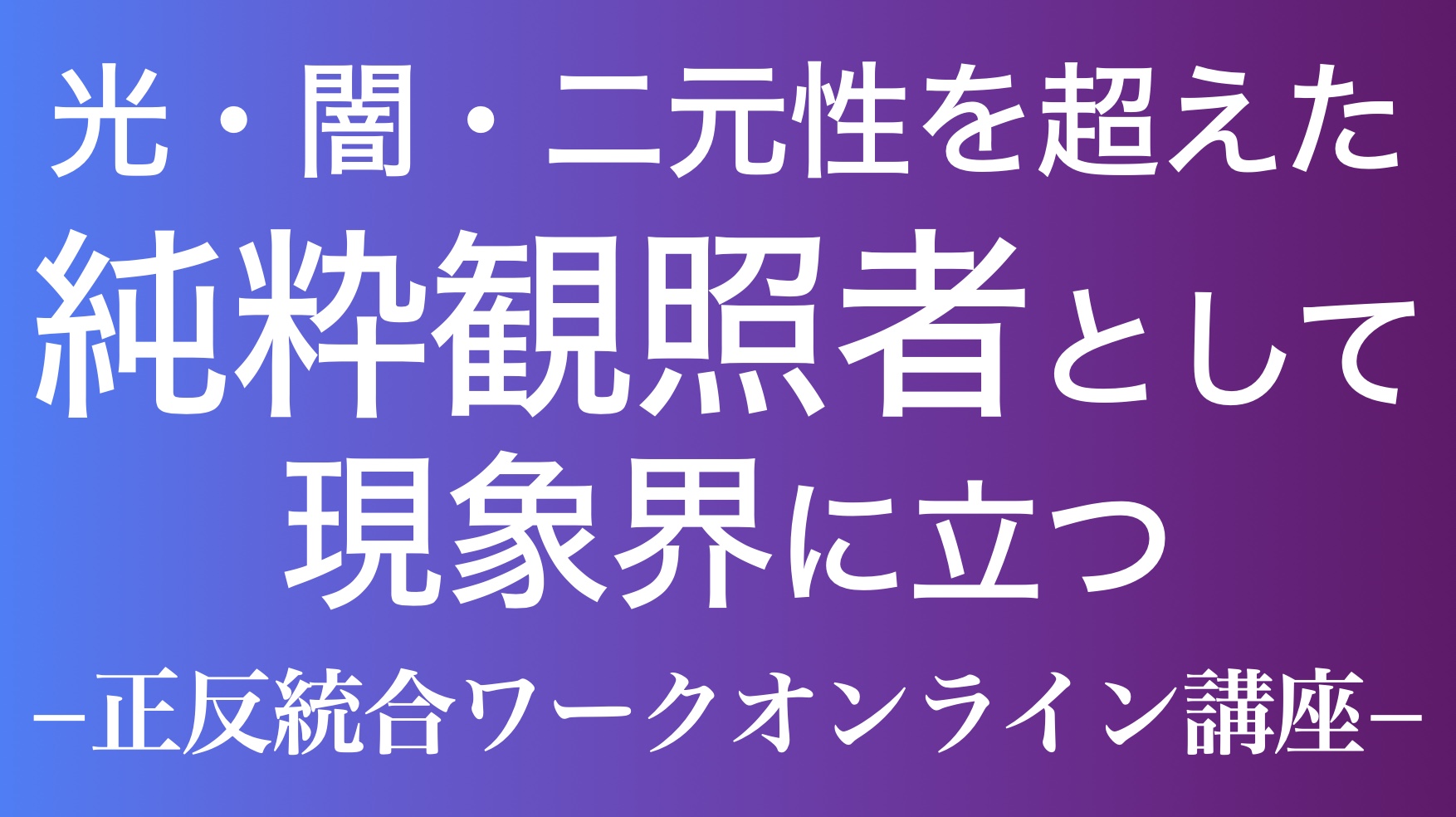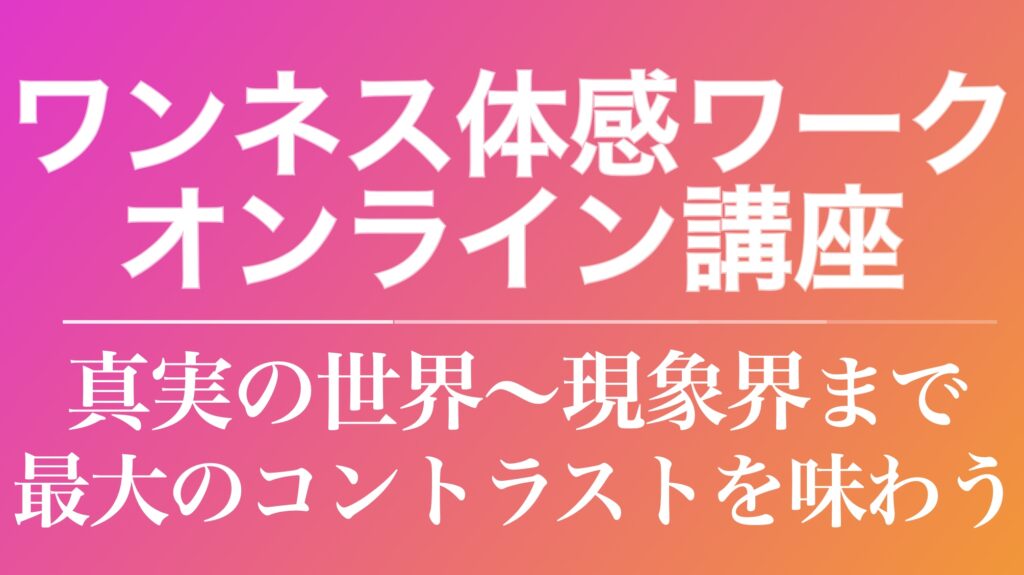ある受講生の方が、講座2.0の本編部分、感情フレーミング、デフレーミングをご覧になって、
ご自身の体調不良とか精神的な問題、睡眠がうまく取れないことなどをテーマにワークをしてくださいました。
補講の「答えの受け取り方」等をご覧になる前でしたが、作った質問についてアドバイスが欲しいということでご連絡をいただきました。
心身のこと、睡眠のことは、程度の大小はあっても誰でも一度や2度は悩んだりするものだと思いますし、
あるいはご自身の課題に置き換えてご覧いただければと思います。
①悩み/現状
②理想の感情と行動
③新しい質問
の順番です。
*
①夜まとまった睡眠(2時間以上の睡眠)がとれない
②夜寝たら朝まで気持ちよくぐっすり眠れる
③もっとぐっすり安心して朝まで眠れるようになるにはどうしたらいいだろうか?どんな工夫が出来るだろう?どんな心掛けが必要だろう?
①体調が悪く、疲れやすい
②やりたいことが不自由なく出来、明るい気分でいられる
③もっと体調が良くなって楽しく過ごすためにどんなことに意識を向けたらいいだろうか?
①物事をネガティブに考え不安になる
②今この瞬間を常に意識し、ネガティブにもポジティブにもならない
③もっと「今ここ」を感じるためには何を意識したらいいだろうか?どんな行動をしたらいいだろうか?どんな工夫が必要だろう?どんな意識づけが効果的だろう?
①自分を信頼しありのままの自分を愛することができない
②自分にもっと優しく、長所も短所も丸ごと愛して自分との信頼を深める
③もっと自分に優しく、ありのままの自分を愛するためには、どんな言葉をかけてあげたらいいだろう?
①自分の本当の心を見つめるのが怖い
②自分の本当の心を知って、自分の望みを知り、行動したい
③何がそんなに怖いのだろう?恐れは何を伝えたいのだろう?
*
メールを拝見して、本当に良い感じで意識の方向性(ゴール)を決めて質問を作っていただいていると思いました。
例えば
・もっとぐっすり安心して朝まで眠れるようになるにはどうしたらいいだろうか?
・どんな工夫が出来るだろう?
・どんな心掛けが必要だろう?
といった質問をする「前」と「後」では、意識が「変化する」ことを感じられると思います。
それがごくわずかだとしても、まずはこの「変化」を大切にしたいですね。
そして顕在意識ではっきり答えがわからなくても、無意識化ではすでに変化が起こっています。
結局は僕らにとって実際的に効力を持つのは、「無意識」です。
顕在意識にとって「わかる」必要は必ずしもありません。
逆に言うと顕在意識でわかっているつもりになっていても、無意識に浸透していなければ効果は薄いかもしれません。
(まとまって眠るかどうか?体調をどうするか?なども、無意識が決めていますよね?)
そして、補講の「答えの受け取り方」の内容になりますが、質問するときのステート(状態)にも意識を向けたいですね。
例えば、
「夜眠れないな…。昨日も一昨日も。今夜もだろうか。なんで眠れないんだろう?」
と思考が回っているところを想像していただいて、
その思考・ステート(状態)に入り込んだ状態になってください。
(多分、視線、顔は下を向いて、猫背気味になったりすると思います)
この状態でも、もちろん感情フレーミングやデフレーミングは効果を持ちます。
例えば「これまでより少しでもスムーズに睡眠に入るためにどんな工夫ができるかな?何に意識を向けたら良いかな?」とか、質問しないよりは、質問する方がいいでしょう。
「とりあえず、こうやって布団があって、雨風凌げるって有難いことだよね。災害がなく、避難する必要ないことに感謝しよう。たとえ眠れなくても横になって体を休めよう」といったとことに意識を向けると、まったく向けないよりは、気分がよくなるかもしれません。
次に、
上を向きながら、少し口角をあげて、視線も上に向けて、胸を開いたり、両手を広げたりあげたりしながら、
「今まで以上に安心して朝までぐっすり眠れるように、どんな工夫が出来るだろう?何に意識を向けたらいいだろう?」
といった感じで、質問してみてみます。
(子供が好奇心を持って、純粋にシンプルに問いかける感じ)
そして、また「意識の変化」を感じてみます。
これだと、きっと質問する前後で、意識の変化、違いを感じられると思います。
(猫背のステートがよくない状態で質問するよりも、さらに良いと思います)
この違いで分かることは、
無意識化では変化していて、答えがわかっている(わかり始めている)ことです。
何か具体的な答え・イメージなどが、顕在意識にわかる形で上がってこないとしても、気分がいい・気が楽になる・何だかすっきりした・呼吸が楽になった・視界が明るくなった気がするなどなど、変化があるほど、無意識化の変化があることがあります。
繰り返しになりますが、僕らにとって、実際的な効力をもっているのは無意識です。
また顕在意識でわかるには、タイムラグが必要だったりします。
例えば、
翌日、お風呂に入っている時に「あ!こうしよう」と思いついたり、
誰かのアドバイスを通じて「なるほど!」
ってなったりしますよね。
何かの本が気になって読んだり、何かのセミナーに参加してみよう、という気になったりします。
*
一方で、
質問したその場で解るためには(多少慣れも必要かもしれんが)、
「私はどんな答えを受け取ったんだろう?」といった「顕在意識がわかるためのコマンド」をかけて、
微細な反応から意味を拾って、顕在意識上にあげていくこともできます。
(これも補講の「答えの受け取り方」と内容が被りますが)
いずれにしても、自分への問いかけになります。
*
そして
言葉の「選び方」もさらに工夫できるかもしれません。
できるだけ「幼い子供に対しても安心して問いかけられる言葉」を選ぶのもひとつのアイディアです。
無意識は強力ですが、顕在意識が扱うような複雑な言葉が必ずしも浸透するわけではないので、そのための工夫として、「3〜5歳くらいまでの子供がわかる言葉を選ぶ」ことをしたりします。
それから人にもよりますが、
「どんな工夫が必要だろう?」という質問の「必要」には、少し「力み」がはいってしまうかもしません。
一般的には「必要」という言葉に、「義務」とか「べき」といった硬い印象をもちそうです(集合無意識にそう刻まれています。)「ノルマ」のようなもの連想させるかもしれません。
もちろん、
純粋な感じ・軽い波動・印象で、「必要」という言葉を使えれば、全く問題ありません。
言葉は、純粋には記号であり、本来、良い悪いはありませんので。
ですので、幼児に対して、
「どんな工夫が必要なの?」と聞くこともできますが
例えば「どんな工夫ができるかな?」とにっこり微笑みながら聞く場合とで、
幼児の反応は変わってきそうですよね?
ちょっと想像してみるのもいいかもしれません。
さらに、「楽しく」とか「楽々と」といった感情・状態を前提として入れてもいいですよね
*
そして比較の言葉として、
もしも、「もっと」をこれまで長く使ってこられて「やや使い古されている」感があるとすれば、
「べつの比較の言葉」を使うのも選択肢です。
また他に考えられることとして、
「もっと」という言葉に、ネガティブな印象や苦しさを感じたり、
(どうにかしなきゃとか、なんとかしたい、など切羽詰まった感覚やイメージほか)
(例えば、子供の頃に大人から「もっと・・・しなさい!」とよく言われたとかもある人は、そうかもしれないですね。だとすると良くないイメージなのについ使ってしまったりします)
もしこれまでの経験で「もっと」では答えを得にくい、変化しにくいという経験があるとしたら、
これからも「変化しにくい」という経験をかさねてしまうかもしれません。
皆さんは、いかがでしょう?
「もっと」という言葉に良い印象を持たれますか?
楽しくなったり、前向きになりやすいですか?ニュートラルな感じでしょうか?
それとも、やや飽きのようなものを感じる(新鮮な感じがしない)でしょうか?
例えばですが…
もっと体調が良くなって楽しく過ごすためにどんなことに意識を向けたらいいだろうか?
↓
今までにありえないような最高の体調を体現して、今この瞬間に300%ワクワクで楽しむ自分を今体現するとしたら、何に意識を向けるだろう?
といった質問をすると(極端かもしれませんが)、
思わず、ぐっとガッツポーズをとったり、上を向いて、最高の状態の自分のエネルギー・波動の少なくとも一端には触れてしまったり、見えてしまうとか、
何か新鮮な感じが得られるのではと思います。
すでにその最高の自分は存在していることを無意識レベルではもちろん知っていて、
顕在意識上でもそのフレーバーは感じることになります。
だれか尊敬する人、憧れの人の意識を借りるのもいいですね。
「あの◯◯さんなら、こういうときに、最高に・・・・になるために、どんな意識で、どんな表情で、どんなエネルギーで、どんな行動をするだろう?」
こうした質問をしてから生じる、小さくとも変化することを大切にしたいと思います。
*
そして
これも既存とかぶってしまうところがあるのですが
1)質問のバリエーションを増やすこと(脳・意識に新しい刺激)
2)質問の回数も増やすこと
をしていきたいところです(無理のない範囲で)
今回メールくださった方は、もうすでにこうした工夫をしていただいてると思います。
例えば、
「①物事をネガティブに考え不安になる」
に対して、
いくつもの質問を用意さています。
いずれ、内側で気づきを得らたり、
「あ、質問でこんなに変わるんだ!」といった発見をされるなど、
いわゆる成功体験を積むことで、
↓
<自分に聞くこと>の信頼感がさらに増して、
↓
今回教えてくださった「さらに先の質問」にも到達されるようになると思います。
つまりは、
今回教えてくださった「どんな意識づけが必要だろう?」の
答えは、
新しく出てくる「さらに先の質問」になります。
「新しい質問」=「答え」だなんて、なんだか変な感じがするかもですね。
それでも例えば
デフレーミング的に、
「そもそも私がネガティブと感じているのは、どのような判断(基準)からだろう?」
「その判断の仕方・在り方は、どのくらい正しい(or楽しい)のだろうか?」
「この状況が人生のギフトだとしたら、ここから何を学べばいいんだろう?」
もしここで何かの気づきを得られるとしたら、ネガティブって何なんだろう?と質問が湧くかもしれません。
同じような質問の仕方としては、
「自分を信頼する」って何を意味するんだろう?どうしたいと思ってるんだろう?
私は本当は何を得たいんだろう?
などと聞いていくと、
「本当の課題」が浮き彫りになってきたりします。
「本当の課題」とは本当に人それぞれですが、
実は単純な小さな一歩を踏めるかどうか?と言うことから開ける場合もあります。
例えば
ブログに1記事投稿する、さらにそこから日々悩みながらも100回続けた頃には、自分を信頼できるようなっていた、
といった感じです。
(すごく単純な例ですが)
*
比較の言葉+良い感情の感情フレーミングは、
本当の初期でも、分かりやすく、かつ効果的なレシピとして紹介しています。
普通の人にとって、ポジティブ・ネガティブは当たり前に存在し、その中で右往左往するのが人生だったりします。
受講生の皆さんは、
ポジティブ・ネガティブというフレーム、世界から抜けていかれる方だと思います。
ぜひ、より大きなフレームに気づかれ、デフレーミングを継続いただければと思います。(その先に全体性・ワンネス)
*
改めて、この方はの質問はどれも素晴らしいです。
例えば、
①自分の本当の心を見つめるのが怖い
に対して、
②で、望みを明確にされ
③「何がそんなに怖いのだろう?恐れは何を伝えたいのだろう?」
という質問は
極めて的確だと思います。
ただおっしゃるとおりで、恐れていることですから、
なかなか答えらしきもの出会えないのも、また自然なことなのかもしれません。
だから
まず焦らないことと、
すぐにわからなくても自分にOkを出すことはされてもいいのかなと思います。
この辺の「自己信頼」も、
今後、質問する→答えをもらう、を繰り返していくうちに増してくるはずです。
ひとつ工夫されるとしたら、
「誰かに質問してもらっている」と想像するのもいいと思います。
僕もよくやってます。
僕もすごく感じますが
1人で自問自答して答えが出てこなくても、
コーチングの先生や、カウンセラーに質問してもらうと、
答えにつながりやすかったりします。
そう言う意味でも、
特典の個人セッションや、追加購入の60分個人セッションを
利用される方もいらっしゃいます。
経営者・政治家といったプレッシャーのかかる人たちは良く「人に質問してもらうこと」を活用しています。
時間の関係でそこまでしなくても、
お一人で目を閉じて(または開けたままでも)、
何かのセミナーの先生とか、コーチの先生とか、または信頼している方が
目の前に来てくれているのを想像しながら、
その人に質問されて、答えようとすると、
今まで以上に、ご自身の内側に入れるかもしれません。
*
それにしてもこうして自分に質問していくことは、本当にいいですね!
こうして「意識的に質問する」過程で、おのずと
「現象(体調、思考、性格etc)」
または
「現象(体調、思考、性格etc)を、変えたい・取り除きたいと思う自分(自分のいち部分)」
を観察する意識として立っている自分に、気づきを深めていきます。
「悩む自分」ではなく、「質問する側の自分」に入る。
個人の小さな意識よりも、観察する意識。さらには観照意識の入り口に立ち始める。
「意識は体の中にあるように思っていたけれど、
本当は外にも大きく広がってるんだ」
といった気づきに至るかもしれません。
*
花粉症については
「〜で何をえているんだろう?」
「〜は僕に何をもたらしてくれているんだろう?」
といったシンプルな質問です。
の動画でお話ししていますので、もしお時間ありましたら(すでにご覧になってるかもしれませんが改めて)ご覧頂ければと思います。
*
*
*
今回ご質問くださった方は、
質問して明確に答え・反応がわからない時の対処法(追加質問する&待つのバランス)、
「比較の言葉」「質問中の言葉」のバリエーションを増やすこと、
デフレーミングとして以下が参考になったこと
- 「そもそも私がネガティブと感じているのは、どのような判断(基準)からだろう?」
- 「その判断の仕方・在り方は、どのくらい正しい(or楽しい)のだろうか?」
- 「この状況が人生のギフトだとしたら、ここから何を学べばいいんだろう?」
- 「もしここで何かの気づきを得られるとしたら、ネガティブって何なんだろう?」
- 「自分を信頼する」って何を意味するんだろう?どうしたいと思ってるんだろう?私は本当は何を得たいんだろう?
などを教えてくださいました。
皆さんとっても参考になる部分があれば幸いです。